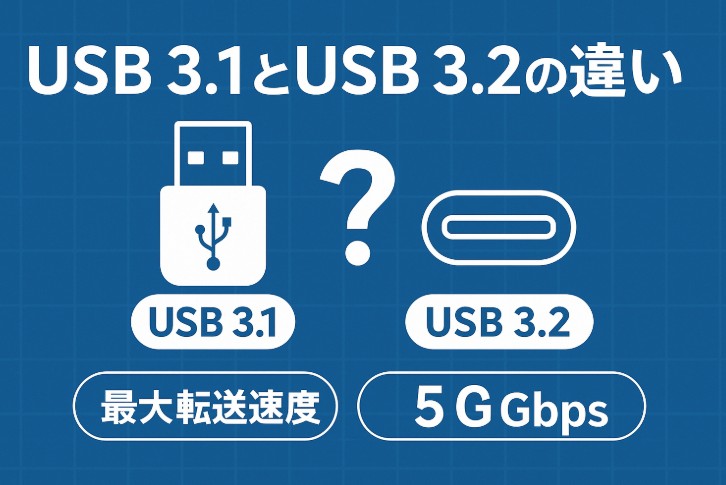「USB3.1とUSB3.2って、どう違うの?」
新しいガジェットやPC周辺機器を買おうとしたとき、よく目にするこの規格。
でも、見た目は似ているし、名前もややこしくて正直よくわからない…という人も多いはずです。
実はこのUSB規格、単なるバージョン違いではなく、転送速度や互換性に大きな違いがあります。
そして、ケーブルやポートの種類を間違えると、せっかくの高速性能がまったく活かされないなんてことも。
この記事では、USB3.1とUSB3.2の違いを「中学生でもわかるように」やさしく解説。
さらに、用途別のおすすめや、これからのUSB規格の動向までまるっと網羅しています。
「USBって難しそう…」と思っていた方も、この記事を読めばもう安心です!
\話題の商品をランキングでチェック/ 楽天ランキングペ ージはこちら<PR>
USBの規格はなぜこんなにややこしいのか?
規格名と実際の速度が一致しない理由
USBの規格名は、一見すると単純そうですが、実は混乱の元になることが多いです。というのも、「USB3.0」「USB3.1」「USB3.2」と名前が変わってきているにもかかわらず、実際の速度や中身はそこまで劇的に変わっていないからです。たとえば、USB3.0は後に「USB3.1 Gen1」や「USB3.2 Gen1」と呼ばれるようになりました。つまり、名前が変わっただけで中身は同じ規格というケースもあるのです。
このように、同じ技術に対して複数の名称があるのは、業界団体(USB-IF)がマーケティングや世代の区別のために名称変更を繰り返してきたためです。消費者にとっては非常にわかりにくく、「どれが速いの?」「互換性あるの?」といった疑問がつきものになります。速度だけを見ても、名前と一致していないことがあるため、しっかり調べてから使う必要があります。
例えば「USB3.2 Gen2」と書かれていれば、最大10Gbpsの転送速度ですが、「USB3.2 Gen2x2」になると20Gbpsに対応しています。しかし見た目ではなかなか区別がつきません。このような背景から、USBの名前だけではなく「Gen表記」とその実際の速度を確認することがとても大切になっています。
USB3.0から始まる混乱の歴史
USB2.0までは、規格もシンプルでわかりやすいものでした。USB2.0は最大転送速度が480Mbps(0.48Gbps)で、長年スタンダードな接続として使われていました。しかし、次世代規格のUSB3.0が登場したことで状況が一変します。USB3.0は最大5Gbpsと大幅なスピードアップを果たしましたが、その後の名称変更が混乱の原因となりました。
USB3.0はのちに「USB3.1 Gen1」と名前を変え、さらにその後には「USB3.2 Gen1」となります。一方で、USB3.1(本来の次の世代)は「USB3.1 Gen2」→「USB3.2 Gen2」と呼ばれるようになります。そして最終的には「USB3.2 Gen2x2」という、さらに速い規格も登場しました。
このように、まるで数学の式のように複雑化していった名称に、一般ユーザーが混乱するのも無理はありません。特に商品パッケージやスペック表では、旧称と新称が混在していることがあり、「USB3.1」と書かれていても「Gen1」なのか「Gen2」なのかを確認しないと、本当に欲しい性能が得られない可能性があるのです。
名前が変わっただけ?USB3.1と3.2の真実
結論から言えば、USB3.1とUSB3.2は「中身が同じで名前が違うだけ」のパターンが多いです。たとえば、USB3.1 Gen1はUSB3.0と全く同じものであり、それがまたUSB3.2 Gen1へと名前を変えています。つまり、これら3つはすべて「最大転送速度5Gbps」の同じ技術です。
では、USB3.2が新しいからといって全部が高速かというと、そうでもありません。USB3.2 Gen2までは最大10GbpsとUSB3.1 Gen2と同じ性能。違いがあるのは「Gen2x2」だけで、これは最大20Gbpsの転送が可能です。なので、単純に「USB3.2と書かれている=速い」とは限らないのが、ユーザーを混乱させる大きな要因です。
このような背景から、USBの規格は「名前」よりも「Gen表記」と「転送速度」に注目するのが正解です。商品を選ぶときは、パッケージの裏側や公式サイトでスペックをしっかり確認することが重要です。
新しい「Gen」表記とは何か?
USBの「Gen(ジェン)」という表記は、「Generation(世代)」の略です。これは、USBの内部規格がどの世代の技術で作られているかを示すものです。例えば、「USB3.1 Gen1」は第一世代のUSB3.x規格で、最大転送速度は5Gbps。一方、「USB3.1 Gen2」は第二世代で、最大転送速度は10Gbpsになります。
このGen表記は、USB3.2の時代になるとさらにややこしくなります。なぜなら、USB3.2では同じGen1でも「USB3.2 Gen1=5Gbps」、「USB3.2 Gen2=10Gbps」、「USB3.2 Gen2x2=20Gbps」と、それぞれ性能が異なるからです。
つまり、USB3.2と書かれていても「Gen1」ならばUSB3.0と同じ、「Gen2」ならばUSB3.1 Gen2と同じ、「Gen2x2」だけが真のUSB3.2といえる進化形になります。この違いを正しく理解しておくと、製品選びで失敗することが少なくなります。
ユーザーが混乱する理由を図で解説
以下は、USB規格の名称と実際の速度の対応関係をまとめた表です:
| 表記名 | 旧称 | 最大速度 | 実際の世代 |
|---|---|---|---|
| USB3.0 | – | 5Gbps | Gen1 |
| USB3.1 Gen1 | USB3.0 | 5Gbps | Gen1 |
| USB3.2 Gen1 | USB3.1 Gen1 | 5Gbps | Gen1 |
| USB3.1 Gen2 | – | 10Gbps | Gen2 |
| USB3.2 Gen2 | USB3.1 Gen2 | 10Gbps | Gen2 |
| USB3.2 Gen2x2 | – | 20Gbps | Gen2×2構成 |
このように、同じ「USB3.2」でもGen1とGen2x2では4倍の速度差があります。ユーザーが混乱してしまうのも当然といえるでしょう。
USB3.1とUSB3.2のスペックを比較してみよう
Gen1、Gen2、Gen2x2とは?
USB3.1やUSB3.2を語る上で絶対に外せないのが、「Gen1」「Gen2」「Gen2x2」という言葉です。これらはすべて“転送速度”に関わる重要なキーワードで、それぞれの意味を知っているかどうかで、USB機器の選び方が大きく変わってきます。
まず「Gen1」は、最大5Gbpsの転送速度を持つ規格で、実質的にはUSB3.0と同じです。これが「USB3.1 Gen1」→「USB3.2 Gen1」と名前を変えていきました。次に「Gen2」は、最大10Gbpsの転送が可能です。これはUSB3.1 Gen2やUSB3.2 Gen2で使われており、倍のスピードになります。
そして「Gen2x2」は、その名の通り2レーン(x2)で転送する仕組みを採用しており、最大で20Gbpsという非常に高速なデータ転送が可能です。ただし、このGen2x2に対応しているポートやケーブルはまだ限られており、一般ユーザーにとっては手に入りにくい面もあります。
つまり、同じUSB3.2と書いてあっても、Gen1、Gen2、Gen2x2のどれかで速度が5Gbps・10Gbps・20Gbpsと大きく異なるため、しっかり確認しないと「思ったより遅かった」となるリスクがあります。購入時には必ず「Genいくつか」を確認しましょう。
最大転送速度の違いを数字でチェック
USBの転送速度は、理論値で示されることが多く、以下のようになっています:
| 規格 | 最大転送速度 | 通信レーン数 |
|---|---|---|
| USB3.2 Gen1 | 5Gbps | 1レーン |
| USB3.2 Gen2 | 10Gbps | 1レーン |
| USB3.2 Gen2x2 | 20Gbps | 2レーン |
このように、USB3.2 Gen2x2は2本の通信レーンを使ってデータをやり取りすることで、Gen2の2倍の速度を実現しています。ただし、理論上の速度と実際に出る速度には差があります。たとえば、USB3.2 Gen2の製品を使っても、実際の転送速度は8Gbps前後になることが多いです。
また、転送速度にはPC側のUSBポートの性能や、接続ケーブル、デバイスの内部設計も関係してくるため、表に書かれた速度=必ず出る速度ではないことも理解しておく必要があります。とくにHDDなどの物理ディスクを使っている場合は、ストレージ側の読み書き速度がボトルネックになることもあります。
とはいえ、数値で比較することで「USB3.2 Gen2x2が最速」ということは一目瞭然です。速度を重視したいユーザーは、Gen2x2対応のデバイスを狙うと良いでしょう。
コネクタ形状は同じ?違う?
USB3.1もUSB3.2も、多くの場合「USB Type-C」コネクタを採用しています。ただし、ここで注意してほしいのは「Type-C=高速」というわけではないという点です。実際には、USB Type-A(従来の長方形の形)でもUSB3.2 Gen1やGen2に対応している場合がありますし、Type-Cでも中身がUSB2.0相当の製品も存在しています。
つまり、コネクタの形状だけで判断するのは危険です。USB Type-Cは表裏の区別がなく、挿しやすいという利便性はありますが、「中身の規格」が何なのかが最も重要なのです。
また、Type-CはUSB4やThunderbolt3/4との互換性もあるため、今後ますます重要になってくる形状ですが、すべてのType-Cがすべての機能を持っているわけではありません。「このケーブル、Type-Cなのに遅い!」という声の多くは、実は中身の規格を確認していないことが原因です。
USBの性能を見極めるには、見た目の形ではなく「スペック表」と「Gen表記」が決め手になります。
互換性のあるケーブルとは?
USB規格の互換性を語るうえで、ケーブルの存在は無視できません。どれだけ速いUSBポートを搭載していても、ケーブルが対応していなければ性能は引き出せません。たとえば、USB3.2 Gen2x2のポートでも、USB2.0対応のケーブルを使えば転送速度は480Mbpsに落ちてしまいます。
特に注意したいのはType-Cケーブルです。見た目はどれも同じでも、対応している規格が違う場合があります。以下のように分けて考えると分かりやすいです:
| ケーブル種類 | 対応速度 | 注意点 |
|---|---|---|
| USB2.0 Type-C | 最大480Mbps | 安価な製品に多い |
| USB3.2 Gen1 Type-C | 最大5Gbps | 比較的スタンダード |
| USB3.2 Gen2 Type-C | 最大10Gbps | 動画編集などにおすすめ |
| USB3.2 Gen2x2対応 | 最大20Gbps | 高速SSDなどで活躍するが高価 |
購入前には、「このケーブルはGenいくつ対応か?」「転送速度はいくつまで出るか?」を公式情報でチェックすることをおすすめします。また、「USB認証ロゴ」も一つの目安になります。USB-IFが認証した製品は、基本的に安心して使える性能を保証しています。
実際の使用感にどれほど差が出るのか
理論値だけを見ると「Gen2x2が最強!」と思うかもしれませんが、実際の使用感ではどうなのでしょうか?
結論から言うと、使い方次第で大きく違いが出ます。例えば、大きな4K動画ファイルを外付けSSDにコピーするような作業では、USB3.2 Gen2やGen2x2の高速転送は非常にありがたいです。時間が1/2〜1/4に短縮されることも珍しくありません。
一方で、マウスやキーボード、プリンターなどの周辺機器では、高速転送が必要になることはほとんどなく、USB2.0やUSB3.2 Gen1でも十分です。つまり、用途に応じて規格を使い分けるのが効率的ということです。
また、WindowsやMacのOS側の対応、ドライバーの最適化も影響します。最新規格のUSBを使っても、古いOSでは速度が出なかったり、正しく認識されなかったりすることもあります。最新のデバイスを使う場合は、ソフトウェア面のアップデートにも注意が必要です。
USB3.1とUSB3.2、どっちを選べばいい?
日常用途ならどこまで必要?
普段使いのパソコン操作やスマートフォンとの接続、USBメモリでのデータのやりとり程度であれば、USB3.1やUSB3.2のどちらを選んでも大きな差は感じにくいのが実情です。多くの人が行う作業──たとえば、ドキュメントの保存、写真の転送、スマホの充電、プリンターとの接続──では、USB2.0でも十分対応できます。
ですが、USB3.1 Gen1(5Gbps)以上の規格であれば、大きな画像ファイルや複数のデータを扱うときに体感的にも速さを感じるようになります。特にUSBメモリや外付けHDDをよく使う人にとっては、USB3.1 Gen1またはそれ以上の速度が快適さに直結します。
したがって、一般的な日常使用であれば「USB3.1 Gen1(またはUSB3.2 Gen1)」あたりを基準に選べば問題ありません。最新規格を無理に追い求める必要はなく、「安定して速い」ことが最も重要です。
動画編集やゲームではどちらが有利?
動画編集やゲーム用途となると、USB規格の違いが大きな差を生みます。特に4Kや8Kといった高画質の動画を編集したり、数十GB単位のファイルを頻繁にやりとりする場合は、高速な転送が必要不可欠です。
このようなシーンではUSB3.2 Gen2(10Gbps)やGen2x2(20Gbps)が非常に有効です。たとえば、外付けSSDに直接動画素材を保存して編集するようなワークフローでは、低速なUSB接続ではラグや遅延が発生し、作業効率が大きく下がります。
また、ゲーミング環境では、外付けストレージにゲームデータを置く場合や、VRデバイスなどの高帯域を必要とする周辺機器を使う場合には、転送速度の速いUSB3.2が有利です。読み込み速度が速ければ、ロード時間の短縮にもつながります。
つまり、動画編集やゲーミングには、少なくともUSB3.2 Gen2、可能ならGen2x2を備えた環境が理想です。
周辺機器との相性をチェック
USB規格を選ぶときに重要なのは、自分のPCやデバイスだけでなく、使いたい周辺機器との相性です。たとえば、最新のUSB3.2 Gen2x2対応の外付けSSDを購入しても、パソコン側のポートがUSB2.0しか対応していなければ、その性能はまったく発揮されません。
また、ノートパソコンの中には、Type-Cポートがあるにもかかわらず、実はUSB2.0しか通らないものも存在します。そのため、必ずマザーボードやパソコン本体のスペック表を確認することが必要です。USBの性能は「ポートの見た目」で判断できません。
加えて、ケーブルやハブを使う場合も要注意です。例えば、高速転送対応のデバイスを使っているのに、USB2.0のハブを経由して接続すると、転送速度はUSB2.0の480Mbpsにまで落ちてしまいます。すべてのパーツが対応しているか、一つ一つチェックすることが大切です。
将来性を考えた選び方
今後数年間にわたって使用することを考えるなら、「将来性」もUSB選びのポイントになります。現在はUSB3.2が主流になっていますが、すでにUSB4やThunderbolt 4といったより高速で高機能な規格が登場しています。
将来的に大容量のデータを扱う予定がある方や、仕事でハイエンドなデバイスを使う方は、少し上の規格を選んでおくことで買い替えの頻度を減らすことができます。特にノートパソコンや自作PCでは、USBポートの種類が変更できないため、初期選定はとても重要です。
また、USB4との互換性を視野に入れておけば、今後登場する新しい周辺機器にも柔軟に対応できます。「今は使わなくても、数年後には必要になるかもしれない」──そういった考え方で選ぶと、長期的に見てコスパが良くなります。
安さと性能、バランスのよい選択は?
すべての人が最高性能のUSB規格を必要としているわけではありません。だからこそ、自分の使い方に合った「コスパ重視」の選択がポイントになります。一般家庭での写真管理やOffice作業が中心であれば、USB3.1 Gen1(またはUSB3.2 Gen1)でも十分です。
一方で、多少予算に余裕があるなら、USB3.2 Gen2対応の機器を選ぶことで、将来の使い勝手が大きく向上します。Gen2x2は価格が高く、対応製品も少ないため、現時点ではややマニア向けといえるかもしれません。
バランスを考えるなら、「USB3.2 Gen2対応でType-Cポートがある」製品がおすすめです。速度・汎用性・価格のバランスが取れており、多くのユーザーにとって最適な選択肢になるでしょう。
よくある誤解と失敗例を解説
USB3.2だから速いとは限らない?
「USB3.2対応」と聞くと、多くの人が「これは速い!」と感じるかもしれませんが、実はそう単純ではありません。なぜなら、USB3.2には**Gen1(5Gbps)・Gen2(10Gbps)・Gen2x2(20Gbps)**という3つの異なる速度規格が存在しており、「USB3.2」と書かれているだけではその中のどれなのか分からないことが多いのです。
さらに、商品説明やパッケージには「USB3.2」としか記載されていないことがあり、それがGen1であれば、USB3.0とほぼ変わらない性能しか得られません。これにより、「思っていたよりも転送速度が遅かった」「動画のコピーが全然速くならない」といった声が後を絶ちません。
そのため、「USB3.2」の表記だけでなく、「Gen○」や「最大転送速度○Gbps」という情報をしっかり確認することが非常に大切です。購入時には製品の仕様欄を細かく読むクセをつけましょう。
ケーブルがボトルネックになっていた話
意外と多い失敗が、「高速なUSBポートと外付けSSDを使っているのに速度が出ない」というケースです。この原因の多くは、ケーブルが低速対応だったというもの。見た目が同じType-Cケーブルでも、中身の規格がUSB2.0ということも珍しくありません。
たとえば、USB3.2 Gen2対応のSSDを使っていても、ケーブルがUSB2.0対応であれば、最大速度は480Mbpsに制限されてしまいます。これではせっかくのSSD性能が台無しです。
さらに困ったことに、安価なケーブルの中には仕様表記が曖昧なものや、全く書かれていないものも存在します。そのため、できるだけ「USB認証ロゴ(SuperSpeed+など)」がついた信頼できるメーカーの製品を選ぶのがベストです。
高速通信が必要な用途では、「ケーブル選び」も本体と同じくらい重要だという意識を持つことが、失敗を防ぐカギになります。
充電速度にも違いはあるの?
USBの転送速度ばかりに目が行きがちですが、**充電性能(電力供給能力)**もUSB規格によって異なります。たとえば、USB2.0では基本的に500mAまで、USB3.0や3.1では900mA〜1.5A程度、USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB3.2やUSB4では、最大100W(20V/5A)の高速充電も可能です。
つまり、USB3.2だからといって必ずしも高速充電できるわけではなく、「USB PD」に対応しているかどうかがカギになります。スマートフォンやノートパソコンを高速充電したい場合は、「USB PD対応」「最大電力○W対応」といった表記をしっかり確認しましょう。
なお、充電も通信と同様に、ケーブルとアダプターの両方が対応していないと規格通りの電力が供給されません。特にノートPC充電用として使う際には、対応規格が一致していないと充電速度が極端に遅くなるか、充電できないこともあります。
ポートの色で判断してはいけない理由
USBポートには「青色=USB3.0」「黒=USB2.0」といったイメージを持っている方も多いと思いますが、実はこの色分けはメーカー独自のルールにすぎません。つまり、青だからといって必ずUSB3.0という保証はないのです。
また最近では、Type-Cポートが主流になってきており、Type-Cには色の区別がありません。そのため、パソコンやハブを見ただけでは、どのUSB規格に対応しているかを判断するのは非常に難しくなっています。
確実なのは、製品のスペック表を確認すること。特に「USB3.2 Gen2対応」「最大10Gbps対応」などの記述があるかどうかをチェックしましょう。見た目に惑わされず、データで判断することが失敗を防ぐコツです。
表記にだまされないチェックポイント
USB製品を選ぶときに最も重要なのが、「正確なスペック表を確認する」ことです。以下のようなチェックポイントを押さえておくと、表記にだまされずに済みます:
-
「USB3.2」と書かれていたら、Genいくつかを確認
-
転送速度は理論値と実測値が違うことを意識
-
Type-CでもUSB2.0というパターンに注意
-
ケーブルの規格と長さも影響大
-
信頼できるメーカー・認証マークをチェック
たとえば「USB3.2 Gen2 Type-C」とあれば、最大10Gbpsで高速通信が可能で、互換性も高い優秀な規格です。一方で「USB Type-C(USB2.0)」とだけ書かれていれば、形状は同じでも中身は全く違う性能の製品ということになります。
このように、USBはパッと見ただけでは分からない“落とし穴”が多い規格です。少し面倒でも、詳細を確認することで後悔のない買い物ができるでしょう。
今後のUSB規格はどうなる?最新動向まとめ
USB4ってなにが違うの?
USB4は、これまでのUSB規格と比べて大幅な進化を遂げた最新のインターフェースです。最大の特徴は「最大40Gbpsの超高速通信」「Thunderbolt 3との互換性」「複数のプロトコルを同時に扱える柔軟性」などが挙げられます。これは従来のUSB3.2 Gen2x2の最大20Gbpsを倍にする性能です。
USB4では、映像出力(DisplayPort)やデータ通信、電力供給を1本のケーブルで同時に扱えるため、ノートパソコン1台で複数モニター・ストレージ・電源を一括管理できるドッキング環境がより手軽になります。
また、USB4はすべて「USB Type-C」端子を採用しており、従来のType-Aポートからの完全な転換が進んでいます。ただし、USB4対応と書かれていても、すべての機器が40Gbpsの速度に対応しているわけではないため、速度や機能の詳細は製品ごとに確認が必要です。
Thunderboltとの関係は?
USB4とThunderbolt 3は、実は兄弟のような関係にあります。USB4は、Thunderbolt 3の仕様をベースに開発された規格であり、Thunderbolt 3との互換性を前提に設計されています。つまり、USB4ポートがあれば、Thunderbolt 3対応機器も基本的に利用可能です。
ただし注意点として、すべてのUSB4対応製品がThunderbolt 3をサポートしているわけではありません。メーカーによっては、Thunderbolt互換性を省いたUSB4製品も存在します。そのため、「Thunderbolt 3互換」と明記されているかどうかを購入前に必ずチェックしましょう。
将来的には、Thunderbolt 4がさらに発展した形でUSB4.0規格の中に統合されていく見込みがあり、今後のUSB規格は、速度・利便性ともに大きな飛躍を遂げていくことになります。
USB規格の未来予測
今後のUSBは、「より速く」「より高機能」「より統一されたコネクタ」がキーワードになっていくでしょう。特に注目されているのが、USB Power Delivery(USB PD)による高出力化とThunderbolt機能の統合です。
現在、最大100W(20V/5A)の給電が可能なUSB PDですが、今後は240W(48V/5A)まで対応する拡張規格「USB PD 3.1」も登場しており、ゲーミングノートや高性能ワークステーションなど、これまでACアダプターが必須だった機器のUSB一本化が加速しています。
また、USB規格は徐々に「Type-C一強」へと移行しており、将来的にはすべてのデバイスがType-Cポートで統一される可能性が高いです。AppleがiPhoneでもType-Cを採用したことで、その流れは一層強まっています。
デバイス選びにおける注意点
今後のUSB事情をふまえると、これからパソコンや周辺機器を選ぶ際には以下のポイントを押さえると失敗しにくくなります:
-
USB4またはThunderbolt対応ポートがあるか?
-
PD(Power Delivery)に対応しているか?
-
Type-Cポートの数と位置は使いやすいか?
-
スペック表に速度や互換性が明記されているか?
たとえば、USB4対応のノートパソコンを選べば、将来的に高速なSSDや8Kモニター、複数ディスプレイとの接続にも柔軟に対応できます。また、1本のケーブルで充電・映像出力・データ転送を済ませられるため、机の上もスッキリします。
このように、「今だけでなく将来どう使うか?」を意識したデバイス選びが、これからのUSB環境ではとても重要です。
最新情報をどう追えばいいか
USB規格は頻繁にバージョンアップされ、新しい技術も次々と登場します。そのため、信頼できる情報源から定期的に最新情報をチェックすることが大切です。以下のような方法があります:
-
USB-IF(公式サイト):USB規格の標準化団体
-
メーカーの公式ブログやFAQ
-
信頼できるガジェット系ニュースサイト(GIZMODO、PC Watchなど)
-
YouTubeの専門チャンネル:実際の検証動画が見られる
-
X(旧Twitter)などSNSでのレビューや速報
また、自分が購入したい製品に関するレビュー記事や比較表なども積極的に活用しましょう。とくにケーブルやハブなどのアクセサリーは、スペック偽装があることもあるため、ユーザーの口コミが参考になります。
最新の情報に触れておくことで、数年先を見越した「賢い選び方」ができるようになります
まとめ:ややこしいUSB規格もこれでスッキリ!
USB3.1とUSB3.2の違いは、見た目や名称では判断しにくい“ややこしさ”がありますが、その本質は「Gen(世代)と転送速度」にあります。
単純に「USB3.2だから速い」と思ってしまうと、思わぬ落とし穴にハマってしまうこともあります。
そこで今回の記事では、
-
Gen1(5Gbps)、Gen2(10Gbps)、Gen2x2(20Gbps)という速度の違い
-
規格名称の変遷と混乱の背景
-
ケーブルやコネクタの見分け方
-
用途別のおすすめ選択肢
-
今後のUSB4やThunderboltとの関係
といったポイントをわかりやすく整理しました。
結論としては、自分の用途にあったUSB規格をしっかり選ぶことが何より大切です。
「速さを活かすにはすべてのパーツが対応していなければならない」という点も、ぜひ覚えておいてください。
これからUSB機器を選ぶ方、今使っている環境を見直したい方の参考になれば幸いです!