「五平餅」と聞くと、旅先で見かける素朴な郷土料理というイメージがあるかもしれません。でも実は、家庭でも簡単に作れて、ごはんのおかずやおやつにもなる万能レシピなんです!この記事では、材料3つで作れるたれの簡単レシピから、地方ごとの味の違い、アレンジアイデアまでをたっぷりご紹介。中学生でも作れるレベルのわかりやすい内容なので、料理初心者の方もぜひチャレンジしてみてください!
|
|
五平餅ってどんな食べ物?知っておきたい基本情報
五平餅の由来と歴史
五平餅(ごへいもち)は、主に長野県、岐阜県、愛知県の山間部で昔から食べられてきた郷土料理です。名前の由来には諸説ありますが、一番有力なのは「神様に捧げる“御幣(ごへい)”に似ているから」という説。御幣とは神社で見かける白い紙飾りのことですね。もう一つの説は「五平(ごへい)さんという人が初めて作ったから」という、ちょっと親しみのある説もあります。
この料理はもともと山で働く人たちの簡易なごちそうでした。山で手に入る材料を活用し、ごはんをつぶして成形し、木の串に刺してたれを塗り、囲炉裏や炭火でじっくり焼いて食べるスタイルが定番でした。お米文化の日本らしい工夫が詰まった料理で、お祭りや集まりの場でも振る舞われることが多かったんですよ。
今では道の駅や観光地などで見かけることも多く、素朴な味と香ばしいたれが魅力で、全国にファンが広がっています。
地域によって違う五平餅のカタチと味
五平餅は地域ごとに「形」も「味」も個性豊かなんです。例えば、長野県の南信地方では「わらじ型」と呼ばれる楕円形が定番。一方、岐阜県の飛騨地方では「団子型」といって、丸いお団子を串に3つほど刺したスタイルが多く見られます。
形の違いには、使われる串の素材や焼き方の影響もあります。平らな形はたれをたっぷり塗れて香ばしく仕上がり、団子型はもちもち感がしっかり味わえるのが特徴です。
味にも違いがあります。信州ではくるみやごまを使った香ばしいたれが多く、飛騨地方ではしょうゆベースのあっさりとしたたれが人気。甘めが好きな人は中津川のピーナッツ入りたれにハマるかもしれませんね。
旅行先で見つけた五平餅を食べ比べるのも、ひとつの楽しみ方です!
五平餅に使うお米の種類とは?
五平餅に使うお米は、基本的にはうるち米が使われます。うるち米とは、私たちが毎日食べている普通のお米のことです。もち米だけを使うと、粘りが強すぎて成形しにくく、焼いたときにくっつきすぎてしまうことがあります。そのため、もち米とブレンドしたり、うるち米100%でつぶして作る家庭が多いです。
つぶし加減にもコツがあります。完全にペースト状にするのではなく、少し粒が残る程度につぶすと、焼いたときの食感がもちもちしていて美味しいですよ。
また、地元の新米を使うと香りや甘みが増して、より五平餅の魅力が引き立ちます。
串の形や材料にも意味がある!
五平餅の串には、木の枝を使うのが本来のスタイルです。特に「ヒノキ」や「竹」がよく使われ、自然の香りがほんのりと加わって独特の風味が楽しめます。また、地域によっては「割り箸」や「竹べら」など、平たい形の串が使われることもあります。
なぜ平たい串が多いのかというと、たれを塗る面積を増やすためなんですね。焼いたときにたれが焦げ目をつけやすくなり、より香ばしくなるというわけです。
もしご家庭で作るなら、割り箸を2本くっつけて代用したり、木ベラを使っても雰囲気が出ますよ。手作りならではの自由なアレンジを楽しんでみてください。
なぜ五平餅が今再注目されているのか?
最近、五平餅がじわじわと人気を集めている理由のひとつは「手作り感」と「郷土の味」への注目です。昔ながらの家庭料理や地域の伝統食が見直される中で、シンプルだけど美味しい五平餅に惹かれる人が増えています。
また、SNSでも五平餅は“映える”と評判。焼き目のついたもち米に、てりっと光る甘辛だれがたまらなく美味しそうに見えるんです。おうち時間が増えた今、家族で作って楽しめるメニューとしても人気上昇中です。
加えて、観光地のご当地グルメとしての注目もあり、地域の魅力を伝える一つのアイコンになっています。手軽に作れるのに本格的な味が楽しめる五平餅、あなたも一度試してみませんか?
たれの種類いろいろ!地方ごとの味くらべ
信州風たれの特徴:くるみと味噌の絶妙コンビ
信州風の五平餅のたれといえば、「くるみ味噌」が定番です。くるみの香ばしさと、信州味噌の濃厚な風味が合わさった味は、一度食べたら忘れられない美味しさ。砂糖やみりんを加えることで、甘じょっぱい味わいに仕上がります。
くるみはすり鉢で細かくするのが伝統的な作り方ですが、ミキサーやフードプロセッサーを使えば簡単です。仕上げにごまを少し加えると、香りがさらに豊かになります。
このたれは、ごはんだけでなく、焼き野菜やおにぎりにもよく合うので、多めに作って冷蔵庫にストックしておくと便利です。
木曽風たれ:香ばしいごまが香るバージョン
木曽地方の五平餅のたれは、ごまの香ばしさが際立つのが特徴です。白ごまや黒ごまをたっぷりとすりつぶして、味噌や砂糖、しょうゆを合わせた濃厚なたれが基本。ごまのコクが加わることで、まろやかでありながらも香ばしい味わいになります。
ごまは香りが命なので、炒ってからすりつぶすのがポイント。すり鉢を使うと一層香りが立ち、手間をかけたぶん味に深みが出ます。フードプロセッサーを使う場合は、加熱しすぎに注意して焦がさないようにしましょう。
このたれは、焼いたときに香りが一層引き立つので、食欲をそそる一品になります。特に秋から冬にかけて、体が温まる味としても人気です。
飛騨風たれ:しょうゆベースのあっさり系
岐阜県の飛騨地方では、しょうゆベースのあっさり系たれが好まれます。味噌を使わず、しょうゆ、砂糖、酒を中心にしたシンプルな味付けで、素材の旨みを活かすのが特徴です。
五平餅の甘辛たれといえば濃厚なイメージがありますが、この飛騨風たれはさっぱりしていて、ごはんとの相性も抜群。焦げたしょうゆの香ばしさがなんとも食欲をそそります。
甘みは控えめで、どちらかというと大人向けの味わいかもしれません。お子さんがいる家庭では、少し砂糖やみりんを多めにして調整すると食べやすくなります。
五平餅以外にも、焼き鳥のたれや炒め物に使えるので、万能調味料として活用できるレシピです。
中津川風たれ:ピーナッツ入りで甘め
中津川市をはじめとする東濃地域では、ピーナッツ入りの甘いたれが特徴です。ピーナッツのコクと香ばしさ、そしてたっぷりの砂糖で仕上げた甘めの味わいは、子どもから大人まで幅広い世代に人気があります。
ピーナッツバターを使えば簡単に再現可能で、味噌としょうゆと合わせて混ぜるだけ。もし砕いたピーナッツが手に入るなら、粒感を残して加えると食感も楽しくなります。
甘めなので、おやつ感覚で食べられる五平餅になります。焼きたてにたっぷり塗って、外側がカリッと中がもちもちの状態でいただくと最高です。
東濃風たれ:しょうゆと砂糖でこっくり濃厚
東濃地方では、味噌を使わずにしょうゆと砂糖をメインにした濃厚なたれが主流です。そこに酒やみりんを加えて、こっくりとした甘辛味に仕上げます。
火にかけて煮詰めながら作ることで、たれのとろみが出て、五平餅によく絡みます。とくに串にたっぷりたれをつけて焼くと、表面がキャラメル状にパリッとして絶品。
このタイプのたれは、保存がききやすいのもポイントです。瓶詰めにして冷蔵庫で保存すれば、2週間程度は風味を保てます。お弁当のおかずや焼き魚に使っても美味しいですよ。
材料3つで作れる!基本の簡単たれレシピ
最短5分で完成!味噌・砂糖・しょうゆで作る
五平餅のたれは、実はとっても簡単に作れるんです。必要なのはたったの3つ!味噌・砂糖・しょうゆだけで、あっという間に本格的な味になります。
分量の目安は、味噌:砂糖:しょうゆ=2:2:1。たとえば味噌を大さじ2にしたら、砂糖も大さじ2、しょうゆは大さじ1。これを小鍋で混ぜながら弱火で加熱し、全体がなめらかになるまで溶かすだけ。たった5分で完成します。
味噌の種類を変えるだけでも味にバリエーションが出るので、赤味噌でコクを出したり、白味噌で優しい甘みを楽しんだり、自分好みに調整できますよ。
余ったたれは冷蔵庫で保存しておけば、いつでも五平餅が楽しめるのも嬉しいポイントです。
ごまをプラスして風味アップ
基本の3つの材料に、すりごまを加えるだけで、風味がグッと豊かになります。白ごま、黒ごまどちらでもOKですが、白ごまはやさしい甘さ、黒ごまは香ばしさが強くなるのが特徴です。
ごまは炒ってからすりつぶすと香りが倍増します。すり鉢がなくても、袋に入れてすりこ木や瓶の底などで押しつぶせば十分です。加える目安は大さじ1~2程度。
ごまを入れることで、たれの味に奥行きが生まれ、ごはんの味もしっかり引き立ちます。また、見た目にもごまのつぶつぶが加わって、より“手作り感”が出て美味しそうに見えるんです。
このレシピは、普段のおかずや弁当用の甘辛だれとしても大活躍します!
ピーナッツバターでコクと香ばしさをプラス
甘くてコクのあるたれをもっと手軽に作りたい方には、ピーナッツバターを使ったアレンジがおすすめです。市販の無糖ピーナッツバターがあれば、材料をそろえる手間も省けて時短にもなります。
作り方はとても簡単。味噌(大さじ2)、しょうゆ(大さじ1)、砂糖(大さじ1)に、ピーナッツバター(大さじ1)を加えてよく混ぜるだけ。小鍋で弱火にかけながら、なめらかになるまでゆっくり混ぜれば完成です。
ピーナッツバターの油分で、たれにツヤが出て口当たりもまろやかになります。風味もナッツ特有の香ばしさが加わり、より一層美味しくなります。
おやつ系の五平餅にぴったりの味なので、小さなお子さんにも大人気。余ったたれはトーストに塗ったり、焼き野菜のディップとして使うのもおすすめです。
電子レンジでも作れる時短ワザ
「鍋を使うのは面倒…」という方には、電子レンジでの時短レシピがぴったり。材料を耐熱容器に入れて混ぜ、レンジで加熱するだけで、手軽にたれが作れます。
基本の配合(味噌2:砂糖2:しょうゆ1)を耐熱ボウルに入れ、よく混ぜてからラップなしで500Wで30秒加熱します。一度取り出して混ぜ、再度30秒。全体がトロッとしてなじんでいれば完成!
レンジ調理のコツは、加熱しすぎないこと。加熱時間が長すぎると、味噌が固まってしまったり、たれが分離することもあるので、様子を見ながら少しずつ加熱しましょう。
洗い物が少なくて済むのも嬉しいポイント。1人前からでも気軽に作れるので、少量だけ作りたいときにも最適です。
余ったたれの保存方法とアレンジ術
五平餅のたれは、一度にたくさん作っておくと便利。保存方法のポイントを押さえておけば、日持ちしていろいろな料理にも活用できます。
保存のコツは「完全に冷ましてから密閉容器に入れる」こと。瓶やタッパーに入れて冷蔵庫で保存すれば、1週間〜10日ほどは美味しく使えます。味噌としょうゆがベースなので、冷凍保存も可能。製氷皿に小分けにして凍らせておくと、必要な分だけ使えてとても便利です。
アレンジとしては、たとえばごはんにそのまま乗せるだけで「ごはんの友」に。焼きおにぎりの表面に塗ってトースターで焼けば、香ばしいおやつにもなります。
また、炒め物の味付けや、焼き鳥のたれ代わり、ナスやこんにゃくの田楽風にするのも◎。味噌だれの応用範囲は広く、余すことなく楽しめますよ。
五平餅をおうちで作ってみよう!初心者向けガイド
家庭用炊飯器で作るもち米ベースのごはん
五平餅のベースとなるのは、ごはん。家庭ではうるち米だけでも、もち米と混ぜてもOKです。おすすめは、うるち米3合に対してもち米1合くらいの割合。もちもちしつつも、成形しやすい絶妙なバランスになります。
作り方はとても簡単。まずはいつも通りにごはんを炊き、炊き上がったらボウルに移します。そして、しゃもじやすりこ木などでごはんを半分くらいつぶすようにします。完全につぶすのではなく、少し粒が残るくらいがベスト。
この状態で成形すると、もちもちした中にプチっとした食感があり、五平餅らしい味わいになります。熱いうちに作業すると、粘りが出てくっつきやすくなるので、やけどに注意しながら手早く進めましょう。
冷めてしまうと固まりやすくなるので、手に水をつけながら作業すると、扱いやすくなりますよ。
形作りのコツと串の代用品アイデア
五平餅の形は地域によって違いますが、おうちで作るならわらじ型や団子型が作りやすいです。まずは手に水をつけて、ごはんを小さめのハンバーグ状に成形しましょう。厚さは1.5cm〜2cmくらいが焼きやすくておすすめです。
串がない場合は、割り箸を2本貼り合わせて代用したり、竹串、木ベラ、さらにはアイスの棒などでもOK。形にこだわらず、食べやすいサイズにすることが大切です。
また、おにぎり型にしてたれを塗る「五平餅風焼きおにぎり」にするのも、初心者には簡単で人気のスタイル。子どもと一緒に作るなら、手にラップを巻いて握ると衛生的で楽しい作業になりますよ。
無理なく楽しく、家庭の道具で自由に作れるのが五平餅のいいところですね。
フライパンでもOK!焼き方のコツ
本格的には炭火やグリルで焼くのが理想ですが、**家庭ではフライパンでも美味しく焼けます!**まずは、油をひかずに中火で温めたフライパンに成形したごはんを並べて、両面に焼き目をつけましょう。
焼き色がついたら、一度火を弱めてたれをハケやスプーンで塗り、さらに焼くのがコツ。両面にたれを塗って焼くことで、たれが香ばしくカリッと仕上がり、より本格的な味に近づきます。
くっつきやすい場合は、クッキングシートを敷いたり、テフロン加工のフライパンを使うと安心です。また、たれが焦げやすいので、焼きすぎには注意。軽く香ばしい焼き目がつけばOKです。
トースターや魚焼きグリルでも応用できますので、自分のキッチンに合わせて焼き方を工夫してみてください。
たれを塗るタイミングが美味しさの決め手
五平餅を美味しく仕上げるための最大のポイントは、「たれを塗るタイミング」です。焼く前に塗ってしまうと、たれが焦げて苦味が出やすくなるため、ごはんに焼き目がついた後に塗るのが正解!
片面を焼いたらひっくり返し、焼けた面にたれを塗り、再び裏返して軽く焼きます。そしてもう一度、もう片面にたれを塗って同じように焼くと、両面がカリッと香ばしく仕上がります。
最後にもう一度、仕上げとして軽くたれを塗ると、見た目にもてりが出てとても美味しそうになります。
焦げ目をうまくコントロールするには、火加減を中火から弱火に調整しながら焼くのがポイント。たれの焦げた香りがふわっと広がる瞬間が、まさに食べごろです!
子どもと一緒に作れる楽しいレシピ
五平餅は成形やたれ塗りの作業が楽しいので、子どもと一緒に作るのにぴったりのレシピです。やけどに注意すれば、つぶす・丸める・塗るという工程は、小さな子でも安心して参加できます。
たとえば、ごはんを型抜きでハートや星の形にしてみたり、小さな団子型を作って「五平ボール」にしたりと、自由に遊びながら作ることができます。たれも、ピーナッツバター入りの甘めバージョンにすれば、子どもも大喜び!
作ったものをお弁当に入れたり、おやつタイムに出したりすれば、「自分で作った!」という達成感が得られます。
親子で一緒に食文化を体験する機会にもなりますし、食べ物に興味を持つきっかけにもなりますよ。週末の「食育イベント」として、ぜひ試してみてください!
もっと美味しく!たれアレンジと活用アイデア
ごはんのお供にぴったり!たれだけでごちそう
五平餅のたれは、ごはんのお供としても大活躍します。たとえば、あったかごはんにたれをちょんと乗せるだけで、まるで田楽のようなごちそうに早変わり。甘辛い味噌の香ばしさがごはんの甘みを引き立てて、箸が止まらなくなります。
冷蔵庫にたれを常備しておけば、時間がない朝や疲れた夜でも、すぐにおいしい一品が完成。刻みネギや白ごま、七味唐辛子を加えると、味変も楽しめます。
さらに、たれにマヨネーズを混ぜると、まろやかさがアップしてお子さんにも食べやすい味に。おにぎりの具として中に入れても美味しく、外に塗って焼けば五平焼きおにぎりにもなります。
作り置きしておくことで、毎日の食卓がグッと豊かになりますよ。
焼きおにぎりに塗って香ばしアレンジ
五平餅のたれは、焼きおにぎりとの相性が抜群。シンプルな塩むすびにたれを塗って、トースターや魚焼きグリルで焼けば、外はカリッと中はふんわりの絶品おにぎりに変身します。
作り方は簡単。塩で軽く味付けしたごはんを好みの形に握り、トースターなどで軽く焼いてから、両面にたれを塗って再度焼くだけ。たれは少し厚めに塗ると、焦げ目がしっかりついて香ばしさが際立ちます。
表面がパリッと仕上がったら、最後に青じそや刻みのりを添えると風味がさらにアップ。冷凍保存しておいて、食べたいときにレンチンするのもおすすめです。
お弁当のおかずとしても使えるので、ぜひ試してみてください!
野菜スティックのディップとしても◎
五平餅のたれは、ごはん以外の食材にもバッチリ合います。たとえば、野菜スティックのディップとして使うと、いつものサラダがちょっと特別な一品に。
にんじん、大根、きゅうり、セロリなど、カリッとした食感の野菜にたれを添えるだけで、立派な副菜になります。甘めのたれが野菜の苦みをやわらげてくれるので、野菜が苦手な子どもでも食べやすくなります。
よりディップ感を出したいときは、たれにマヨネーズやヨーグルトを加えると、なめらかでまろやかになり、スプーンですくいやすくなります。
カップに入れておけば、ちょっとしたパーティーメニューやおもてなし料理にも活用できますよ。
鶏の照り焼き風に使うと絶品
このたれ、実は肉料理の味付けにも最高なんです。特におすすめなのが、鶏もも肉を使った照り焼き風レシピ。たれの甘辛さとコクが鶏の旨みを引き立てて、ごはんが進む一品になります。
作り方はとっても簡単。鶏もも肉を両面しっかり焼いて火を通し、最後に五平餅のたれを絡めて軽く煮詰めるだけ。たれに含まれる砂糖と味噌が、自然にツヤを出してくれて、見た目も美しい仕上がりに。
お弁当のおかずや晩ごはんのメインにもなる万能レシピ。さらにごまや七味を加えることで、大人向けの味にもアレンジ可能です。
普段の調味料にちょっと飽きたときに、ぜひ試してみてください!
たれを使った五平餅風おにぎらずレシピ
今人気の「おにぎらず」にも、五平餅のたれはぴったりです。ごはんとお好みの具材をのりで包むだけの簡単レシピに、たれをひとさじ加えると、ぐっとコクのある味になります。
おすすめは、ごはん+たれ+焼き鳥風チキン+レタスの組み合わせ。たれの甘辛さがチキンによく絡み、食べ応えのある主食になります。見た目もカフェ風で、お弁当にもぴったりです。
たれをごはんに混ぜ込むだけでも味がつくので、具材が少ないときでも大丈夫。包んで切ると、断面が美しく、SNS映えもばっちりです。
作り置きして冷蔵庫に入れておけば、朝食や軽食にも重宝しますよ。
まとめ
五平餅は、昔ながらの素朴であたたかい郷土料理ですが、家庭でも簡単に作れて、しかもアレンジ自在な万能レシピです。特にたれは、味噌・しょうゆ・砂糖のシンプルな材料から作れるのに、本格的な味わいが出せるのが魅力。
地方ごとの特色あるたれを楽しんだり、家庭でアレンジして自分好みに仕上げたり。ごはん、肉料理、野菜スティックなどいろんな料理に活用できるのもポイントです。
家族や友人と一緒に作って、地域の味を体験する時間を楽しんでみてください。きっと、あなたのおうちの定番メニューの一つになるはずです。
|
|
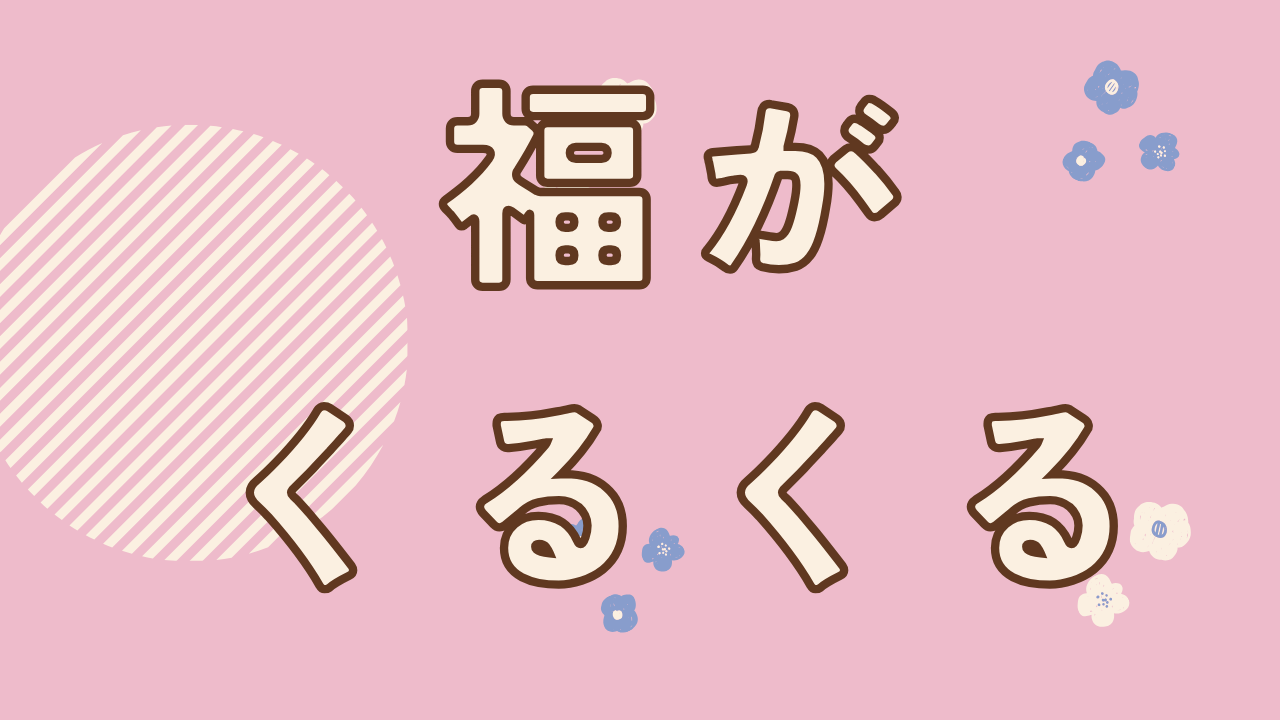
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/372568f6.aa81f931.372568f7.4f92c6b4/?me_id=1391817&item_id=10000097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff212067-nakatsugawa%2Fcabinet%2Fitem%2F001%2F12-045-oya-rv.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1199e59a.098885e1.1199e59b.7cf401e2/?me_id=1270206&item_id=10086478&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fv-drug%2Fcabinet%2F1510%2F4982142012232.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
